こんにちは、yasuです。今回は、世界中で話題となっている日本が開発したAI「ABCI」について解説し、2025年に稼働した「ABCI3.0」についてもわかりやすく解説していきたいと思います。
近年、生成AIや大規模言語モデル(LLM)の発展が世界中で話題になっています。ChatGPTのようなAIも、裏側では膨大な計算を処理できるスーパーコンピューターに支えられています。
そんな中、日本が2025年に稼働を開始したのが「ABCI3.0(AI Bridging Cloud Infrastructure 3.0)」。これは産業技術総合研究所(AIST)が整備した、日本最大級のAIスーパーコンピューターです。本記事では、初心者の方でも分かるように「ABCI3.0のすごさ」と「世界のスーパーコンピューターとの違い」を解説します。
ABCI3.0とは?
ABCI(エービーシーアイ)は「AI Bridging Cloud Infrastructure」の略で、2018年に初代が稼働しました。研究者や企業がクラウド経由で利用できる、オープンなAI研究用スーパーコンピューターです。
2025年に稼働したABCI3.0はその最新世代。特徴は次のとおりです。
- GPUを6,000基以上搭載:NVIDIAの最新GPU「H200」を使い、AIに特化した超並列計算が可能。
- 演算性能はエクサフロップス級:1秒間に10の18乗回の計算をこなせるレベル。従来の2.0と比べて10倍以上の性能向上。
- 大容量ストレージ:75ペタバイトのフラッシュストレージで、膨大なAI学習データを処理可能。
- 高速ネットワーク:GPU同士を超高速で結ぶ通信網により、学習スピードを最大限に発揮。
簡単にいえば「ChatGPTを日本でゼロから作ることも夢ではない規模」の計算資源を持つスーパーコンピューターなのです。
世界のスーパーコンピューターと比べると?
スーパーコンピューターの性能は「フロップス(FLOPS)」という指標で測られます。世界ランキングでは、米国や中国が常に上位を争っています。
ABCI3.0は、AI向け性能(HPL-MxPベンチマーク)で世界第4位、日本国内では第1位を獲得。これは「AI研究に特化した計算能力」という分野で、世界トップクラスに並んでいることを意味します。
ちなみに有名なスパコン「富岳」はシミュレーション(流体計算や気象予測など)に強く、汎用計算分野で世界一を取ったことがあります。一方、ABCI3.0はAI研究に特化した“別軸の世界最強クラスなのです。
どんな分野で使われるの?
ABCI3.0は単なる「速いコンピューター」ではなく、日本の未来を支える重要な基盤です。具体的にはこんな研究に使われます。
- 生成AI・大規模言語モデルの学習
- 医療AI(新薬開発や画像診断支援)
- 自動運転やロボティクスのシミュレーション
- 材料科学・気候変動予測などの大規模データ解析
- 自治体や行政のデータ活用によるスマートシティ推進
学生や研究者にとっては「自分の研究を世界最先端の環境で試せる」大きなチャンスにもなりますよね。
なぜABCI3.0が重要なのか?
- 海外依存を減らす
生成AIの開発は米国のクラウド企業(Google、Microsoft、NVIDIAなど)が圧倒的にリードしています。ABCI3.0があることで、日本も自前で大規模AIを研究できる基盤を確保できます。 - オープン利用が可能
研究者や企業は申請すれば利用でき、料金も商用クラウドより安価。中小企業や学生の研究プロジェクトにも門戸が開かれています。 - AI人材育成にも直結
世界最先端の計算資源を触れる環境は、将来AI研究者やエンジニアを目指す人材にとって貴重な学びの場になります。
まとめ:ABCI3.0は「日本のAIインフラの切り札」
ABCI3.0は、AI研究に特化した世界トップクラスのスーパーコンピューターであり、日本が生成AIや次世代技術で存在感を示すための切り札です。
「ChatGPTのようなAIを日本で作れるのか?」という問いに対して、その土台となるのがまさにABCI3.0。学生やAIに関心のある方は、ニュースとしてチェックしておくだけでも大きな学びになるでしょう。

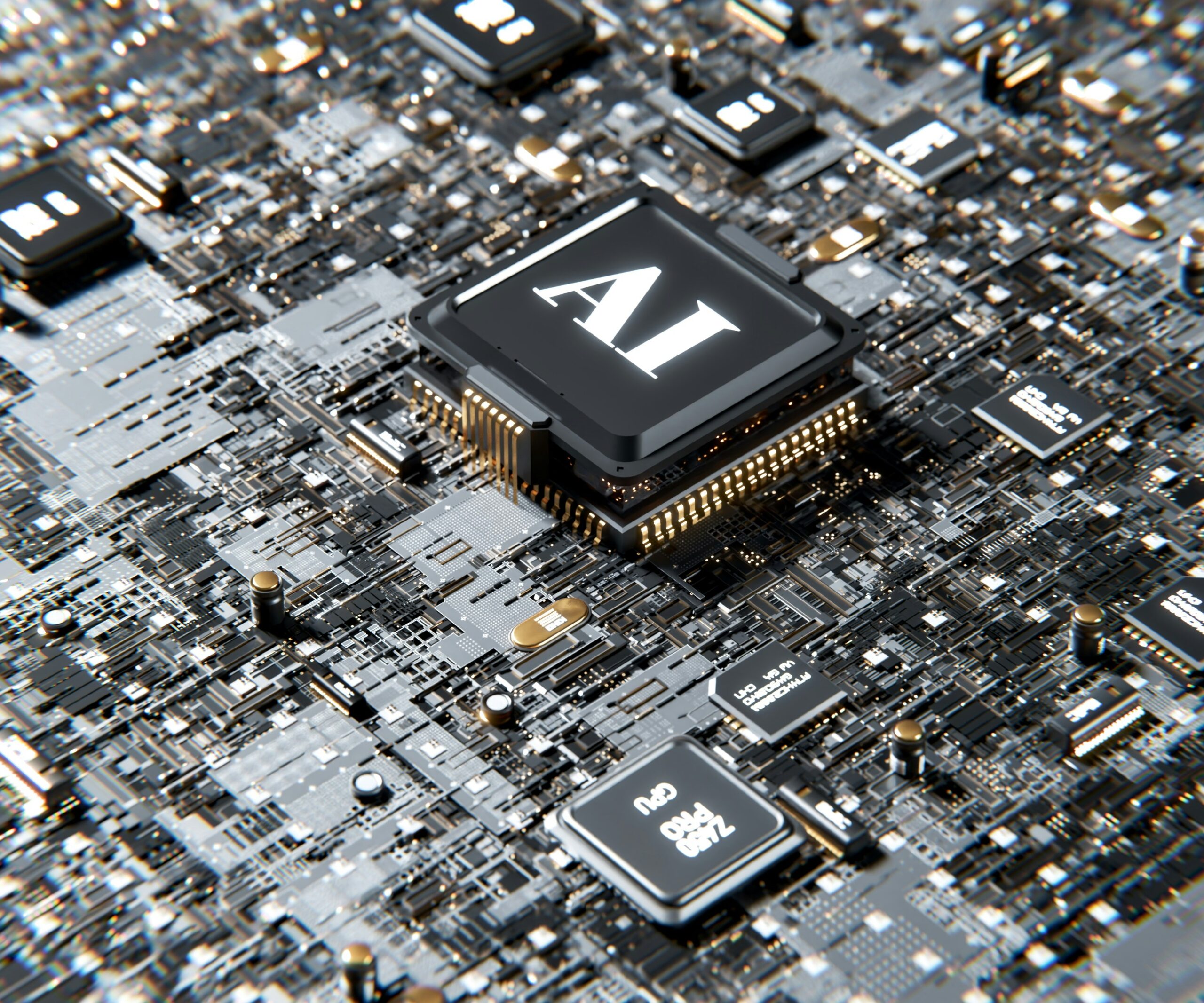


コメント